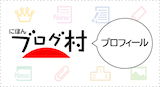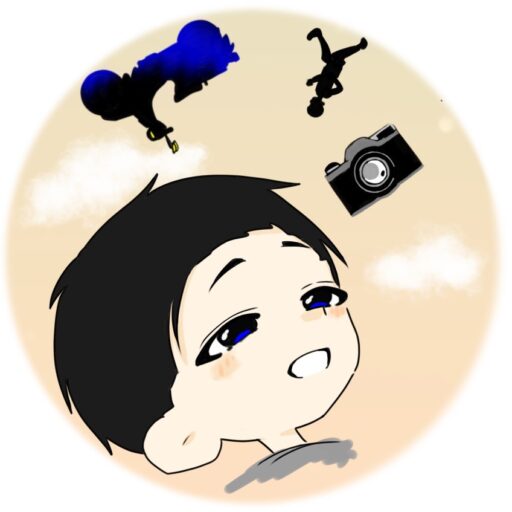今回は宮崎県都城市高崎町という場所に鎮座している神社になります。
龍や鬼にまつわる神社で、本殿に向かう参道の鬼磐階段と呼ばれ鬼が一夜にして作ったと言われる階段があるんです。
もくじ
東霧島神社
霧島六権現の一社に数えられる神社であり、地元では比較的有名な神社という認識です。
私の地元でもある宮崎県ですが、この神社を訪れたのは初めてかもしれません。
記憶を辿れど、思い出すことができないのできっと初めてです。
そんな東霧島神社ですが、どんな神社なのでしょうか。

東霧島神社の御祭神
こちらの神社の御祭神は、「イザナギノミコト」になります。
さらに、天照大御神から神武天皇に至る皇祖を合祀されているのだとか。
そして、十握剣をご奉斎されていると由緒にはあります。
十握剣とは、一つの剣の固有の名称ではなく長剣の一般名詞のようです。
故に、こちらにご奉斎されている剣も他に銘があるのかもしれません。
神社に確認したわけではないので、悪しからず。
創建時期
創建時期は、由緒によると孝昭天皇の時代と伝えられているようです。
孝昭天皇は第5代天皇になり、紀元前まで遡ります。
相当に歴史のある神社です。
ただ、社殿は一度消失されたとも書かれており、西暦963年に再興されたそうです。
それでも、1000年以上の歴史を持つ神社なのだからロマンがあります。
参拝に上られる際は、そんな年月に思いを馳せながらじっくりと歩くのがいいかもしれません。

東霧島神社の見どころ
町中の神社にあやかり隊は、普段住んでいる町にひっそりと鎮座している神社を中心に巡らせていただいています。
ただ、今回は町中というよりは敷地も広い神社となるため、敷地内には見どころも多いです。
そんな見どころ挙げていきたいと思います。
厳つい手水舎
一ノ鳥居をくぐり突き当たりを右に行くと、社務所があります。
その社務所を超えて、奥に進むと石の階段のところに鬼が座っています。

見た目にもインパクトのある赤鬼ですが、左手に金色の瓢箪を抱えており、そこから水が出ています。
これ、手水舎なんですって(笑)
厳つい!
小さい子供は泣いてしまいそうなくらい厳つい手水舎。
こんなインパクトのある手水舎は初めてみました。
振り向くな「鬼磐階段」
鬼の手水舎のすぐ隣に、鳥居があり奥には不揃いな岩で出てきた階段があります。

この階段は「鬼磐階段」という階段だそうです。
鬼磐・・・なんと読むのか・・・多分「おにいわ」かな(汗)
この階段は「振り向かずの坂」とも言われており、一歩一歩踏み締めながら願いを込めて振り向かずに登り切ると願いが叶うとされているのだとか。
鬼磐と名前は、伝説によるとこの辺りを困らせていた鬼が一夜にして積み上げたそうです。
なぜ鬼が石段を積み上げたのか、伝説では村に住んでいた気品のある娘を嫁にせんがために再三口説いていたそうですが、娘も頑なに拒まれていたそうなんです。
豪を煮やした鬼は田畑を荒らして村人は大変困り霧島の神にどうにかしてくれと頼んだのだとか。
霧島の神は、鬼たちに「神殿に続く階段を一夜にして一千段積むことができれば、願いが叶うだろう」と言ったのだとか。
一夜にして一千段の階段は無理だろうと思っていた神ですが、相手は鬼。
とてつもない腕力で次々と石段を積み上げていきます。
これでは、鬼たちの願いが叶い悪が蔓延ってしまうと神は困りました。
そこで、鶏を集めて鳴かせたそうです。
これに鬼たちは、夜明けが来ると勘違いして九百九十九段で石を積むのをやめて退散したのだとか。
まさに紙一重のタイミングだったんですね(笑)
それにしても、夜明けを恐る鬼・・・太陽を恐る鬼・・・なんか漫画でありましたね。
神門の龍
さて、そんな鬼磐階段を登っていくと神門が現れます。
その神門にも注目です。

神門を守るかのように、頭上に龍が飛んでいます。
この龍がかっこいいんです。

参拝者を迎え入れてくれる龍ですが、凛々しい姿がかっこいいと思いませんか?
本当にかっこい龍なので、他の参拝客の邪魔にならなければじっくりと見てほしいです。
神社創建の始まりとされる岩
本殿のある境内に入ると、お社の側に岩があります。
古代磐境信仰の岩だそうです。

磐境とは神を祀るための神聖な場所です。神社の原型ともいうべきものかな。
霊感とかスピリチュアルな波動といったものを私は持っていないし、感じることも少ないですが凛とした空気があって素敵なところでした。
それは境内全体から感じれるものでもありましたね。
神石
見どころの最後は、「神石」です。

写真は神石を正面から見たものですが、この石・・・実は裏に回るとこうなっています。

なんとスパンと切られてように分かれているのです。
引きの写真も載せておきます。

これ、二つに切られているように見えますが、三段に切られているのだそうです。
どう見ても二つなんですけど・・・もう一つはどこにあるのでしょうか。
確かに、後ろに傾いている石は傾いている面もスパンっと切られたように滑らかです。
埋まっているのだろうか・・・。
ちなみに、なぜこのような形になっているのかというと。
イザナギノミコトが十握剣で三段に切った石。
イザナギの妻であるイザナミが火の神であるカグツチを産んだ際に大火傷を負って命を落とします。
そんなイザナミを思ってイザナギが涙し、その涙が石となったのが神石なのだそうです。
そして、悲しみの塊である神石を今後このような悲しみを世人が負うことのないようにと自らの腰にあった十握剣で三段に切ったという伝説があるようです。
悲しみを断つだけでなく、悪縁を断つというご神徳もあるかもしれませんね。
最後に
いかがだったでしょうか、東霧島神社。
いくつもの伝説が残る神社で、素敵なところだと思っていただけましたでしょうか。
この他にも、お社の中には見事な龍の彫刻が施された二つの柱や根元を潜ることのできる大きな楠など見どころは他にもあります。
また、参拝に上られた人なりの魅力を得られると思います。
この記事を書いているのは2024年12月31日の大晦日。
辰年最後の日に龍にまつわる神社の記事を書けて幸せです。
まだまだ、町中の神社にあやかり隊の活動は続きますがひとまず今年の締めくくりとして東霧島神社をご紹介させていただきました。
この先も皆様にご多幸がありますように。
神社情報
〒889-4504 宮崎県都城市高崎町東霧島1560